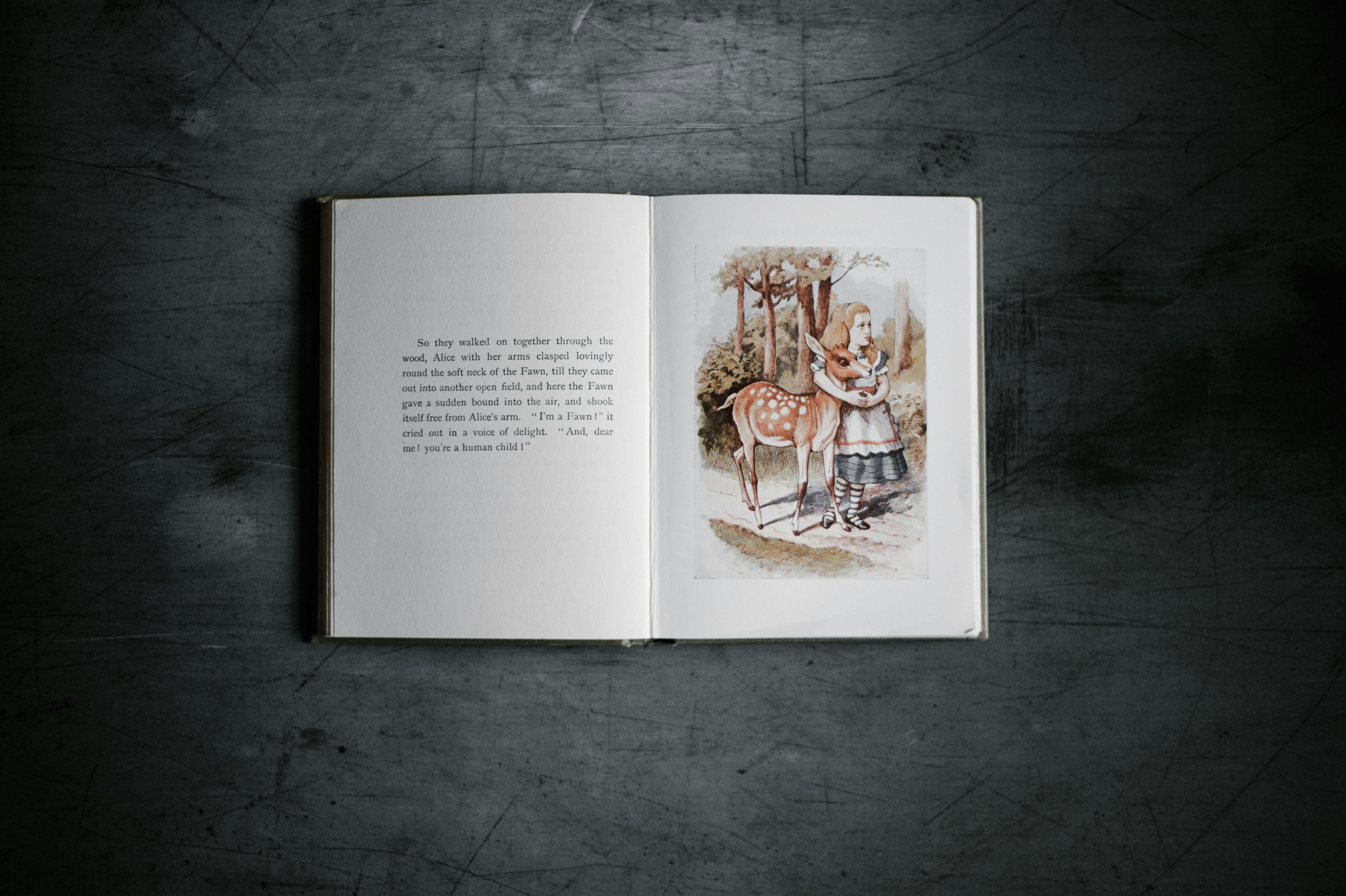フラメンコ教室エルソル ブログ
2024.05.14
ある生徒さんのセビジャーナス特訓
少し前に、お子さんの結婚披露宴でセビジャーナスを踊るという目標に向かって個人レッスンに通ってくださった方がいました(昔フラメンコを習った経験がある方)。
私も友人の結婚披露宴でセビジャーナスを踊ったことが何回かあり、新婦が踊っている姿も見たことがありますが、親が踊るというのもいいですよね!
その生徒さん、長いこと触っていなかったカスタネットも一生懸命練習して再び使えるようになり、本番は華やかで、ご本人にとってもご家族にとっても楽しい思い出になったようで良かったです。
2024.05.04
グラナダの美しい季節(フラメンコブログ フラメンコ教室エルソル)
今頃はグラナダにある庭園の花々がとてもきれいな時期ではないかなと思います。
グラナダの思い出話と一緒に、グラナダの歴史、スペイン語豆知識も少し。
★~★~★~★
2024.04.16
スペイン人の名前のこと(フラメンコブログ フラメンコ教室エルソル)
先日、ビクトルエリセ監督の新作「瞳をとじて」を観ました。
出産間近の妻が、娘にはフアナと名付けたいと言うと、夫が「フアナは古くさい。エストレージャがいい」と言う場面がありました。
数年前に観た「ペトラ」という映画でも、主人公のペトラが自分の名前を「古めかしい名前でしょう?」と言っていたので、スペイン人の名前にも時代によって違いがあるのかなと思いました。
スペイン人の名前について思ったことを書いた投稿です。
★~★~★~★
「スペイン人の名前のこと」(フェイスブックの過去の日記より)
2024.04.14
セビージャの春祭りの思い出(フラメンコブログ フラメンコ教室エルソル)
「セビージャの春祭りの思い出」(フェイスブックの過去の日記より)
2024.04.06
カーネーションの記憶(フラメンコブログ フラメンコ教室エルソル)
私も早い段階で数人に申し込まれたのですが、その手のダンスの経験がなく恥ずかしくて断ってしまいました。
2024.02.22
グラナダのセマナサンタ(フラメンコブログ フラメンコ教室エルソル)
少し早いですが、セマナサンタを思い出しました。
厳粛で壮大な宗教劇を大勢の人たちと共に見守り、一体感を感じた素晴らしい思い出です。
セマナサンタに関係するいろいろな単語も当時覚えたので、それも思い返してみました。
●パソ(キリストやマリア様の像が載った山車)
●コフラディア(カトリックの団体。セマナサンタの行列を取り仕切る。)
●コスタレロ(パソを担ぐ人)
●プレンディミエント(キリストが捕らわれの身になったこと)
●カピローテ(先のとがった頭巾)
●ナサレノ(セマナサンタの装束の人)
●エル・ナサレノ(頭文字が大文字で、キリストのこと)
●エル・カウティボ(頭文字が大文字で、キリストのこと)
★~★~★~★~★
「グラナダのセマナ・サンタ(1997年)」(フェイスブックの過去の日記より)
2024.02.14
フラメンコ教室エルソル 鵠沼教室の看板
今日はバレンタインデーですね。
これは数年前に作ってもらった看板です。
色も形も私の好きなチョコレート風。
育児真っ只中の頃は、ストレスでカレ・ド・ショコラ(21枚入り)を3日で食べ切っていました。
私がフラメンコ教室を自宅で始めた理由は、育児で家に引きこもりがちになっている人の役に立ちたかったからです。
フラメンコに興味ある方、ぜひご連絡ください。
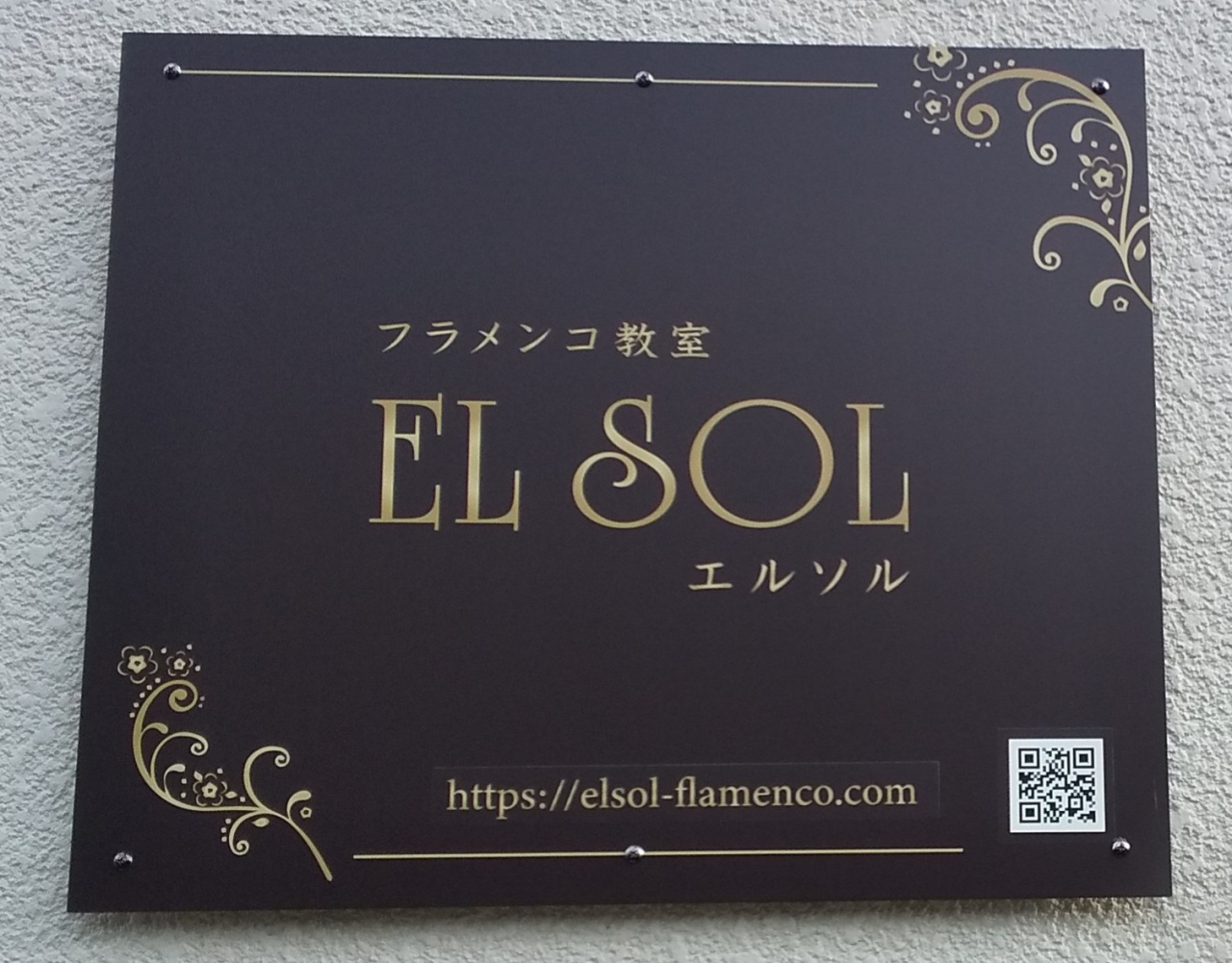
2023.12.23
娘のアンダルーサ(フラメンコブログ フラメンコ教室エルソル)
「娘のアンダルーサ」(フェイスブックの過去の日記より)
娘が先月あったピアノの発表会でグラナドスのアンダルーサを弾きました。
約1年間練習してきました。
「今度弾く曲はアンダルーサっていうの」と娘から聞いた時は感激しました。
アンダルーサに「Playera」という副題がついていることを私は初めて知りました。 Playeraはアンダルシア民謡でカンテホンドと関係があるそうです。
楽譜にはPlayeraが哀しみ、嘆き、祈りと訳されていたので、そういうものがカンテホンドなんだなあと思いました。
土臭さを表現する感じで弾くといいんだって、と言いながら練習していて、どんな風に聴かせてくれるのか私は楽しみにしていました。
夫は、娘がヘッドホンをして電子ピアノの鍵盤をぱこぱこ叩いている音しか聞いていなかったので、アンダルーサを本番で初めて聴いて、こんな哀愁があって美しく力強い曲をいつの間にか弾けるようになっていたんだと驚いていました。
娘がアンダルーサを弾く姿は、私にとっては感慨深かったです。
娘は今はアルベニスのタンゴを練習中です。アルベニスはどんなタンゴの踊りを見てインスピレーションを受けたのだろうと思いました。
ちなみにアルベニスもグラナドスも亡くなった年齢が同じ48歳。 ちなみに私も今48歳。
ああそんな早くにと思いました。
(娘が中3の時の投稿)
2023.12.03
2023年12月2日(土)、湘南アイパーク「健康・移動をデータで結ぶ未来」に参加。
2023年12月2日(土)
ーHEALTHCARE MaaS 2023ー
「健康・移動をデータで結ぶ未来」
藤沢の湘南アイパークで開催された、健康と長寿を考えるイベントに参加させて頂きました。
夕暮れ時のような写真ですが、お客様にはヘルシーランチセットを召し上がりながらショーを見て頂きました。
カフェテリアステージにお越しくださいましたお客様、ありがとうございました。
フラメンコは年を重ねるほどに楽しくなります。
踊りのことだけでなくて、フラメンコを通じてつながる人間関係もとても大きなものです。
カンテの礼子さん、ギターのじゅんさん、どうもありがとうございました。


2023.11.26
フラメンコ教室エルソル 第11回発表会を行いました。
2023年11月25日(土)、藤沢の新堀ライブ館のセゴビアホールにて第11回発表会を行いました。
急に寒くなった日でしたが、お越しくださいましたお客様方、ありがとうございました。
毎日忙しい中一生懸命に練習してきて、生徒さんも素晴らしかったです。
来年の夏の発表会も楽しみですね。頑張りましょう。
ギターの宮川明さん、カンテのレイコシミズサンギットさん、どうもありがとうございました。